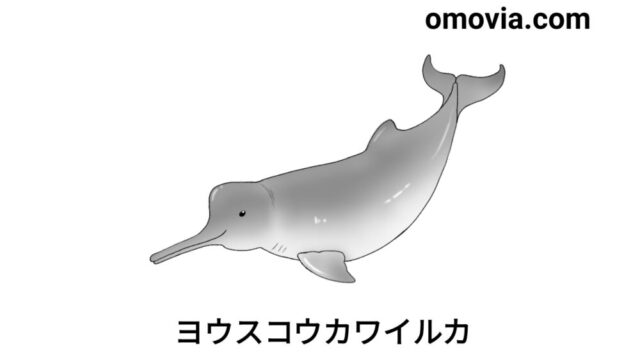モーリシャスクイナとは
モーリシャスクイナ(学名:Aphanapteryx bonasia、英名:Red Rail)は、ツル目クイナ科に属する鳥類の1種です。
インド洋西部のモーリシャス島だけに生息していた鳥ですが、すでに絶滅してしまいました。
標本は残っていないため、いくつかの骨とスケッチ、記述の中にしかその姿を見ることができません。
この鳥に残されている絵の多くは、ヨリス・ヘフナゲル(en:Joris Hoefnagel)がイラストにしたものです。
神聖ローマ帝国の皇帝ルドルフ二世が1600年前後に行っていた動物ショーで公開されていたものを題材にしたようです。
また得体が知れないとされていますが、フランチェスコ・バッサーノの描いたArca di Noè という絵にもモーリシャスクイナらしきものが描かれています。
(ただしバッサーノは、1638年にオランダがモーリシャスを海外領土とする以前の1592年に死去しており、この鳥の出所はよくわかっていません。)
オランダ東インド会社に勤務する布商人、ピーター・ヴァン・デン・ブレッケの描画「ドードー、角のある雄羊とモーリシャスクイナ」(1617年)にはタイトルの通り、モーリシャスクイナの姿があります。
また、鳥獣画を得意としていたオランダ生まれの画家ルーラント・サーフェリーの「絶滅鳥ドードー」(1626年頃、ロンドン自然史博物館蔵)には二羽のモーリシャスクイナが、ドードーの後ろに描かれています。
モーリシャスクイナの特徴
モーリシャスクイナの体の特徴ですが、大きさはニワトリよりも大きくて、体長50cm前後だったと言われています。
羽毛は全体的にやや赤みを帯びた茶色をしており、まるで髪の毛のようにふわふわとしていたようです。
くちばしは長く、すこし曲がっています。足は頑丈で体の割に長かったようです。スケッチなどでは尾は羽毛で隠れていて、どの様なものなのか、生きている状態で観察された記録がないので、はっきりとわかってはいません。
他のクイナ科の鳥の特徴と同じとすれば、尾羽は短く、角張るか丸みを帯びていたのではないかと思われます。体も「側扁」といって、体を左右から押しつぶしたように平たかったのではないでしょうか。
これはクイナ科の鳥に多い特徴で、これにより、茂みを移動することが得意なのだそうです。このような姿だったのではないかと推測されます。
全体的な印象としては、ニュージーランドに生息しているキーウィに似た姿だったようです。
モーリシャスクイナの分布・生息地について
クイナ科の鳥類は世界に130種類ほど生息しています。クイナ科は鳥類の中でも飛ばない種が出やすいことで知られています。
日本では沖縄本島に生息している「ヤンバルクイナ」が有名です。大陸から遠く離れた大洋の孤島に分布するものも多くおり,その中には固有種や固有亜種(世界でその島あるいは諸島にしかいない種や亜種)で飛べないものが多くいます。
クイナ科鳥類の生息地域は、日本、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、アフリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピン、マダガスカル、ソロモン諸島など広く分布しています。
モーリシャスクイナは、インド洋西部のモーリシャス島の固有種でモーリシャス島だけに生息していました。
モーリシャス島とはアフリカ大陸の近く、マダガスカルの東約900kmに位置する小島です。マスカリン諸島に属し、モーリシャス共和国の主島になります。面積は2040㎢(沖縄本島の1.5倍のサイズ)、年平均気温は24~29度です。
モーリシャス島は10世紀以前にアラブ人航海者に発見されていました。無人島だったこの地に、1510年にポルトガル人が上陸を始めました。
1598年にオランダ人が島を占領し、1638年からインド航路の物資の補給地として利用しており、1710年まで統治していました。
同じくモーリシャス島の絶滅種「ドードー」もこのオランダ統治の時期に発見されていることから、おそらくモーリシャスクイナもこの頃に発見されたのではないでしょうか。
1602年頃のモーリシャス島に関する記述のほとんどすべてに、モーリシャスクイナについての言及があります。
しかし記述は同じ内容の繰り返しばかりで、生態に関する記述はあまりありません。ただし、「ドードー」と混同もしくは取り違えた記述を元に分類された結果、モーリシャスクイナを指す名前はいくつもあります。
モーリシャスクイナの絶滅した原因
17世紀前半にオランダ人の本格的な植民が始まってから、ほぼ60年後の1700年前後にはモーリシャスクイナは絶滅したとされています。
絶滅した原因は、主に二つです。一つ目はその肉が美味であり食用として乱獲されたことです。二つ目の原因は外来の生物によって、卵を食べられた可能性です。
一つ目の原因についてですが、狩りの教本によると、モーリシャスクイナを捕まえるのは非常に簡単だと書かれてあります。
肉は美味しかったらしく、焼いて食用にすると豚肉の代わりにできると記述されています。島には人の食用になりそうな大きな哺乳類はいませんでした。
そんな島で飛ばない鳥は、空に逃げられないので捕まえやすく、モーリシャスクイナは乱獲の被害にあってしまったのでしょう。
同様の理由で、世界には他にも、特に島に生息していたクイナ科の鳥たちには絶滅した種が多くあります。
二つ目の原因についてですが、モーリシャス諸島のような島嶼部では、人間により持ち込まれた動物によって生態系が壊れ、生息数が減少してしまうことがあるようです。
モーリシャス島の場合は、人間に持ち込まれた動物は豚やヤギだったので、直接成鳥が食べられたわけではありませんが、同時に船に便乗して入ってきたネズミに卵が狙われ、結果として数が減ってしまったようです。
この島に限らず、今はまだ存在しているクイナ科の鳥も、このような被害にあっている種がいるそうです。島嶼のクイナ類の現状は島の生態系のもろさをもっとも端的に表しているということができます。
島における進化と絶滅の法則
モーリシャス島は火山活動によって生まれた島なので、アフリカ大陸やマダガスカルとは陸続きになったことがありません。
島にたどり着くには、空を飛ぶか、波に流されてやって来るしかないので、モーリシャス島にはコウモリ以外の哺乳類は入って来られませんでした。そのため、もともとこの島には大型の捕食者がいませんでした。
おそらくモーリシャスクイナの祖先はアフリカ大陸やマダガスカルから飛んで来たと思われます。
そして、この島には先ほど述べた理由から、幸か不幸か天敵がいませんでした。鳥は飛ぶ必要のない環境下にいると、敢えて飛べない身体に進化を遂げることがあるそうです。
長い時間をかけて飛べるようになったのにも拘らず、また長い時間をかけて、飛ばなくてもいいように進化していくそうです。なお、クイナ科の鳥は飛翔力を失いやすい傾向があり、飛ばない種類が多数存在しています。
しかし、鳥たちの進化は仇となってしまいます。鳥たちのパラダイスに入り込んだ人間にたやすく捕まり、外来生物を持ち込まれ、結果として絶滅へと追い込まれてしまったのです。同じようなことが世界の島では起こっています。
生存の可能性
最近になって、絶滅したと思われていたクイナ科の鳥が、「反復進化」という稀なプロセスを経て生き延びていたという事実が、ポーツマス大学他によって発表されました。この調査を行ったのはイギリスのポーツマス大学と、自然歴史博物館の研究者たちです。
「反復進化」とは、異なった時代に同じ先祖から枝分かれした種が、その後平行しながら、似たような進化を繰り返すことです。これがクイナで確認されたのは今回が初めてだということです。
証明されたのはモーリシャスクイナではなく「ノドジロクイナ」です。場所はインド洋に浮かぶサンゴ礁が隆起してできた「アルダブラ環礁」。
「環礁」とはサンゴ礁が環状につながった地形のことです。アルダブラ環礁はマダガスカルの北端からは約430km北西にあり、モーリシャス島からも近いところにあります。
もともとノドジロクイナはマダガスカル島に生息していたようです。環境の変化から大量に移住した際、アルダブラ環礁にも辿り着きました。そして、その島には捕食者がいなかった為、飛ばない進化を遂げたようです。
しかし、アルダブラ環礁では大規模な浸水が起き、島は沈下、全体が海へ沈み、飛べないクイナも含むあらゆる動植物が一掃されることになってしまいました。
研究者はその後、地層から出てきた化石を分析しました。すると三万年の間に海水面が下降し、環礁は再び飛べないクイナの生息地になったことがわかりました。
また、海水に覆われる前の時代と、海水面が下がった時代の2つのクイナの骨を比較してみると、ある特徴がわかったのです。
後の時代のクイナの骨は、一掃されてしまったクイナの骨よりも、羽はさらに飛べない進化を、おまけに足首まで飛べない状態に進化を遂げていたことがわかったのです。
つまりこのことは、マダガスカルにいたクイナ科の1つの集団が環礁に定住し、そしてその都度、独自に飛べないようになっていったことを表しています。
マダガスカルにいた一つの種から数千年の空白期間を経て、飛べない2つの種がアルダブラ環礁で生じたのです。この話は、クイナにとって特徴的で、孤立した島にうまく定住し、複数回に渡って飛べないよう進化したこれらの鳥の能力を具体的に証明するものです。
まとめ
「反復進化」の例は、モーリシャス島の話ではありませんでしたが、起こりえない話ではないと思われます。場所も近く、何より同じクイナ科の話です。
長い時間をかけて、またモーリシャスクイナが発見される日が来るかもしれません。その時は、人間が関わることによって絶滅に追い込んでしまった種に対し、同じ過ちを繰り返さないようにしたいものです。